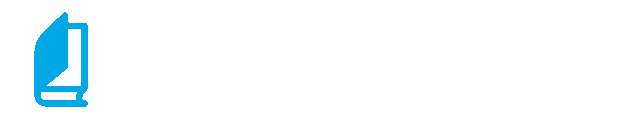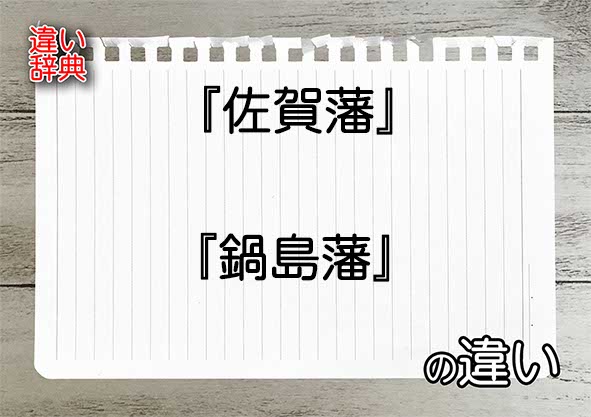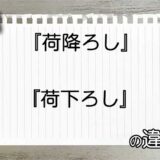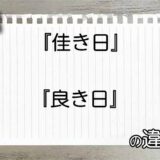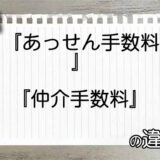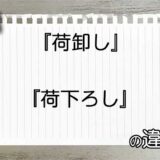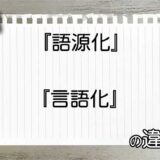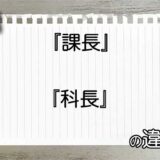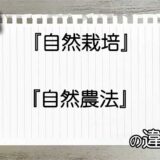この記事では『佐賀藩』と『鍋島藩』の違いについて簡単にわかりやすく解説させて頂きます。
佐賀藩と鍋島藩は、いずれも日本の歴史において重要な藩であります。しかし、両者にはいくつかの違いが存在します。
それでは詳しい内容を深堀り、理解を深めていきましょう。
『佐賀藩』の意味とは
佐賀藩(さがはん)とは、江戸時代に存在した日本の藩の一つです。藩主は鍋島家であり、佐賀県を治めていました。佐賀藩は、国内外の交易や文化の発展を促進し、経済的な繁栄を築きました。
【『佐賀藩』の読み方と品詞】
– 読み方:さがはん
– 品詞:名詞
【『佐賀藩』の言葉の使い方】
– 「佐賀藩の歴史を学ぶ」
– 「佐賀藩の文化を堪能する」
『鍋島藩』の意味とは
鍋島藩(なべしまはん)とは、江戸時代に存在した日本の藩の一つです。藩主は鍋島家であり、佐賀藩を支配していました。鍋島藩は、戦国時代から江戸時代にかけての動乱期において、領地の拡大や城の建設などを行い、力強い藩として知られています。
【『鍋島藩』の読み方と品詞】
– 読み方:なべしまはん
– 品詞:名詞
【『鍋島藩』の言葉の使い方】
– 「鍋島藩の歴史を研究する」
– 「鍋島藩の城を訪れる」
『佐賀藩』と『鍋島藩』の違い
『佐賀藩』と『鍋島藩』の違いは、以下のとおりです。
1. 藩主の家名:佐賀藩は鍋島家が藩主であり、鍋島藩は同じく鍋島家が藩主です。
2. 支配地域:佐賀藩は佐賀県を治めていましたが、鍋島藩は佐賀藩を支配していました。
3. 活動内容:佐賀藩は国内外の交易や文化の発展に力を注ぎ、経済的な繁栄を築きました。一方、鍋島藩は領地の拡大や城の建設など、力強い藩として知られています。
まとめ
『佐賀藩』と『鍋島藩』は、日本の歴史において重要な藩でありますが、藩主の家名や支配地域、活動内容などに違いがあります。佐賀藩は経済的な繁栄を築き、鍋島藩は力強い藩として知られています。それぞれの藩の歴史や文化に触れることで、日本の歴史をより深く理解することができます。